主な規定
主な規定
-
【法第10条】
暴力的要求行為の要求等の禁止何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為(27の行為)をするように要求したり、依頼したり、唆したりすることが禁止されています。また、指定暴力団員が暴力的要求行為をする現場に立ち会い、手助けすることも禁止されています。
-
【法第12条の3及び第12条の5関係】
(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
周辺者による不当要求の規制の強化指定暴力団員が周辺者(「事件共犯者」、「暴力団関係企業従業者」、「元組員(指定暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)」、「金品贈与者(指定暴力団員に、継続的に又は反復して金品等を贈与等している者)」)による不当要求を助けることを禁止するとともに、指定暴力団の威力を示すことを常習とする元組員、金品贈与者等による不当要求が禁止されることとなりました。
不当要求行為を「要求する」、「依頼する」、「唆す」のほかに「助ける」ことも規制対象となる。
-
【法第15条の2、第15条の3及び第46条関係】
(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
対立抗争に伴う市民の危害防止に関する規定の整備対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る暴力行為が人の生命等に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、更に同様の暴力行為が行われるおそれがある場合に、公安委員会が当該対立抗争に係る指定暴力団等を、特定抗争指定暴力団等と指定するとともに警戒区域を定め、警戒区域内での事務所の新設、居宅付近のうろつき等対立抗争を誘発する行為の禁止や既存事務所への立ち入りを禁止することとなりました。また、違反した場合は、直罰規定があります。

-
【法第16条、第17条】
暴力団に加入することを強要したり勧誘する行為、
加入の強要等の規制
暴力団から脱退することを妨害する行為も禁じられています。指定暴力団員が相手方に対し、暴力団に加入することを強要したり勧誘する行為や、暴力団から脱退することを妨害する行為も禁じられています。
指定暴力団員が相手方の妻や親等を威迫して、その相手方を暴力団に加入させたり、組抜けを妨害する行為も禁じられています。
指定暴力団員が、配下の組員に対して加入の強要等の行為を命じたり、他の組員に対して加入の強要等の行為を依頼するなどの行為も禁じられています。
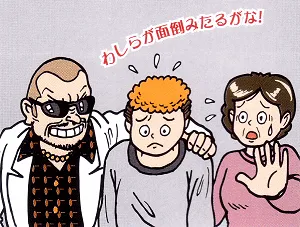
-
【法第20条、第21条】
指詰めを強要するなどの行為、
指詰めの強要等の規制
指詰めの強要等の行為を依頼するなどの行為も禁じられています。指定暴力団員が他の組員に対して指詰めを強要するなどの行為も禁じられています。
指定暴力団員が、配下の組員に対して指詰めの強要等の行為を命じたり、他の組員に対して指詰めの強要等の行為を依頼するなどの行為も禁じられています。

-
【法第30条の2から第30条の4までの関係】
(平成20年5月2日公布、8月1日施行)
損害賠償請求等の妨害行為の規制指定暴力団員が、損害賠償請求や事務所撤去のための請求をし、又はしようとする者やその配偶者等に対して、不安を覚えさせるような方法で請求を妨害する行為を禁止し、その違反者又は違反のおそれがある者に命令することができます。
命令違反には3年以下の懲役又は250万円以下の罰金が科せられます。 (罰則法第47条)
- 【禁止行為の具体例】
- つきまとうこと、執拗に電話をかけること、乱暴な言葉で威迫すること、行動を監視していることを告げること、動物の死骸を送りつけること

-
【法第30条の5関係】
(平成20年5月2日公布、8月1日施行)
対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制対立抗争等における暴力行為により刑に処せられた指定暴力団員に、その指定暴力団の他の指定暴力団員が賞揚・慰労の目的で金品等を供与するおそれがある場合に、公安委員会は当該他の指定暴力団員又は当該指定暴力団員に、当該金品等の供与をし、又はこれを受けてはならない旨の命令をすることができます。
命令違反には3年以下の懲役又は250万円以下の罰金が科せられます。
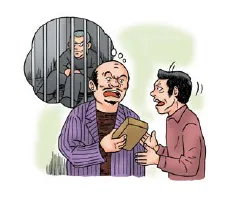
-
【法第30条の6及び第30条の7関係】
(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
用心棒行為等に関する規定の整備指定暴力団員が縄張内で営業を営む者のために用心棒の役務を提供すること等を禁止するとともに公安委員会が当該行為の中止又は防止のための命令をすることができるようになりました。
また、営業者が指定暴力団員にこれらの行為を要求等することも禁止しました。
- 【禁止行為の具体例】
- 用心棒行為、訪問による押し売り、面会による債権取り立て

-
【第30条の8及び第46条関係】
(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
不当要求に伴う市民に対する危害防止に関する規定の整備指定暴力団員等が暴力的要求行為等に関連して人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為を行い、かつ、更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがある場合に、公安委員会が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等を特定危険指定暴力団等と指定するとともに警戒区域を定め、警戒区域内における不当要求を禁止(直罰規定)するほか、不当要求目的で行われる面会要求等に中止命令を発することとなりました。また、事務所の使用制限命令が発せられます。

-
【法第32条及び第32条の2関係】
(平成24年8月1日公布、平成25年1月30日施行)
適格都道府県センターによる暴力団事務所使用差止請求制度国家公安委員会から認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センター(適格都道府県センター)は、指定暴力団等の事務所の付近住民等で当該事務所の使用等の差止めの請求をしようとする者から委託を受けたときは、その者のために自己の名をもって、当該請求に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有することとなりました。
大阪府暴力追放推進センターは、平成25年に国家公安委員会から適格都道府県センターの認定を受け、同制度により、令和2年には六代目山口組傘下組事務所、令和3年には神戸山口組傘下組事務所、令和5年には絆會本部事務所に対し、事務所の使用差止を裁判所に申立て使用禁止の仮処分の決定を受けています。

-
【法第32条及び第32条の2関係】
(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
暴力団員による不当な行為の防止に関する国等の責務及び民間活動の促進に関する規定の整備国及び地方公共団体は指定暴力団員等を入札に参加させないようにするための措置を講ずるとともに、事業者はその事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない旨が明記されました。
- 【指定暴力団員等とは】
-
①指定暴力団員
②指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。)
③法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの
④指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(③に該当するものを除く。)
-
【法第46条から第52条関係】
(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
罰則の強化暴力的要求行為に対する中止命令違反等に係る罰則が強化されました。
※法違反に対する最高刑が大幅に引き上げられました。1年以下の懲役→3年以下の懲役
100万円以下の罰金→500万円以下の罰金
