情報誌・図書等の購読要求
情報誌・図書等の購読要求について
電話による購入強要の場合
-
❶相手の団体名、所在地、姓名及び用件をはっきり確認する
相手が右翼や同和団体名を名乗るだけで、気後れして確認が不十分になりがちです。勇気を持って確認しましょう。
特に、法的処置をとる場合、相手の特定は必須要件です。「田中」とか「伊藤」とかありふれた姓だけを名乗るケースが多くあります。これだけでは、相手を特定するのに多くの手間がかかります。
会話の内容を録音やメモ(報告書)に残しておくと、後日の紛争の際、有効な証拠となります。あなたは会話の当事者ですから、相手との会話の内容を録音しても法的に何の問題もありません。また、メモは、言葉のやりとりはもちろんのこと、相手の口調を含め、できるだけ詳細に書いておいてください。
同時に相手も録音しているかも知れないことを念頭に置くことも大切です。
-
❷社長、所長、支店長等トップには絶対に取り次がず担当者で対応する
いきなり決定権を持つ者が応対すると、その場で即答を迫られ、よく検討する余裕もなく不利な結果となりがちです。平素から社内での電話の取次ぎ要領を指示して おくと良いでしょう。
何かの不都合でトップが電話に出てしまったら、「そのような件は、○○課(者)に担当させている」と、担当課(者)につなぎ直させるようにしてください。
-
❸不要と判断した場合は、きっぱりと断る
「購入(読)の意志はありませんのでお断りします」「いりません」と、きっぱり断ってください。執拗に要求されても、「何度言われても同じです」と繰り返しましょう。また、購入(読)を断る理由を説明する必要は全くありません。
「結構です」「いいです」は、容認したという口実にされるおそれがあります。また、値段や支払い方法の交渉は、購入(読)を認めたこととされかねません。
「検討します」「上司に相談します」「後刻返事します」は、相手に新たな口実を与えることとなります。とりわけ「こちらから電話します」は避けましょう。
相手は懇願、懐柔、恫喝等々あらゆるテクニックを駆使します。恐れず、侮らず、乗ずる隙を与えないよう、き然とした対応が肝腎です。
政治問題や社会問題に関する論争や議論は絶対に避け、相手の挑発に乗らないでください。
電話対応はできるだけ短くしましょう。そのために、最初に5分あるいは10分の時間制限を明言しておくことも大切です。
来訪しての購入強要の場合
基本的には、電話の場合と同様の対応が必要です。それに加え、次のことに注意が必要です。
-
❶応対場所及び時間の制限
事前に準備しておいた応接室等で応対するのが普通ですが、応接室のドアは開け放っておきます。応接室がない場合は、人から見通せる場所(部屋)を使用しましょう。
もちろん、相手が指定する場所へ出向く必要はありません。
応対時間はできるだけ短くします。最初に20分~30分程度の時間の制限を明言しておきましょう。湯茶を出すことは長居を認めたとされかねません。
用件が終わった場合や制限時間が来た時は、きっぱりと退去を要求してください。これに応じない場合は、110番通報を検討してください。
-
❷応対人数と役割分担
来訪して来た相手の人数より多い人数で応対します。密室での取引は危険です。また、恫喝等による恐怖心を和らげるのに有効です。
応対者の役割を分担します。応対担当、記録(録音)担当、連絡担当、確認(車番や裏付け)担当がいれば、ほぼ万全です。
-
❸相手方及び用件の確認
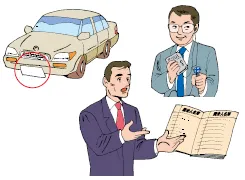
通常の応対と同様に【名刺を要求する・面会人簿冊等に記録させる】等の方法により、相手がどこの誰なのかよく確認しましょう。
来訪の用件についても、相手の口からはっきり言わせましょう。こちらで勝手に憶測しないようにしてください。
送りつけてきた場合
購入(読)の意志がない機関誌、図書等が一方的に送られてきた場合は、次のことを参考に対応してください。
-
❶契約有無の確認
宛名人はもとより、社内関係部署について当該機関誌等の契約の有無について十分確認してください。役員や社員が断り切れずに個人で契約していたケースもあり得ます。
契約の事実があった場合でも、一定の期間内(原則として8日間)であれば「クーリングオフ」制度を利用して、契約を解除する方法があります。
-
❷契約の事実がない場合
令和3年に、特定商取引に関する法律が改正され(令和3年7月6日施行)、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりましたので、あえて当該商品を返送までする義務はありません。
(※改正前は、商品を送り付けた者からの引き取り等に対応するため、送付があった日から起算して14日を経過する日まで商品を保管する必要がありました。)
ただし、契約の事実がない場合でも、その商品が、その送付を受けた者にとって、「営業のために又は営業として締結することとなる」商品である場合には適用されませんので、当該商品の保管義務を負うこととなることから、言いがかりを予防するために拒否の意思表示を明示して返送することも検討するべきです。改正「特定商取引に関する法律第59条」(売買契約に基づかないで送付された商品)
(条文)
【第1項】
販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
【第2項】
前項の規定は、その商品の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結することとなる売買契約の申込みについては、適用しない。 -
❸返送の方法
 【開封前】
【開封前】宛名面に「受取拒否」と明記し、配達員に直接又は郵便局を通じて渡しますと、差出人に返送(無料)されます。
【開封後】郵便にしろ宅配便にしろ、一旦開封すれば受領したとみなされます。この場合は、相手方に引き取り要求を行うか、自費で返送することとなります。
返送する場合、後々のトラブルを避けるため、「配達証明郵便」(注1)で返送することが確実です。
購入(読)拒否の意思表示は電話でも可能ですが、できれば書面のほうが有効です。書面は用件のみ簡潔に書き、「内容証明郵便」(注2)か「配達証明郵便」で相手方 に通知します。
返送する場合の文例
当社は情報誌「○○○○」を注文した事実もなく、購読する意思もありませんので、送付された情報誌を返送します。
また、今後も購読する意思がないので送付しないでください。(注1)「配達証明郵便」:一般書留とした郵便物や荷物を配達した事実を証明するサービス
(注2)「内容証明郵便」:いつ、いかなる文書が誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度
